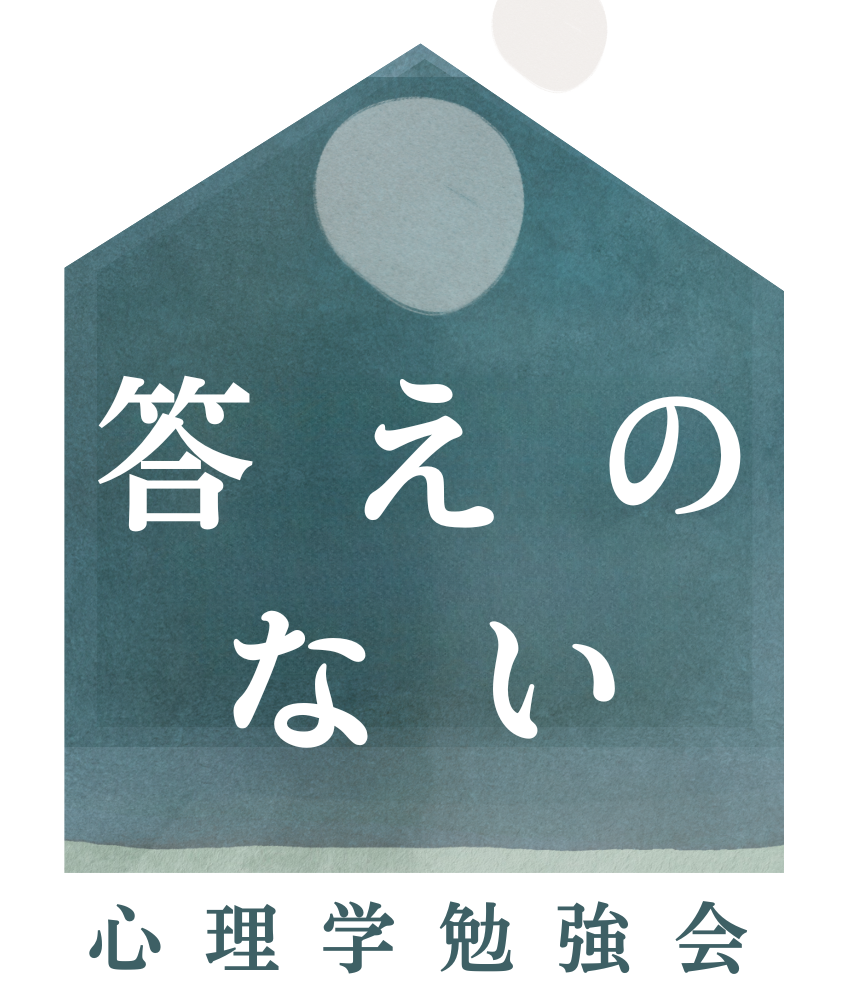救急救命士つぶさんの声
私は、妻と息子と娘の4人で、平凡に暮らしている田舎の救急救命士です。息子は1308gという「極低出生児」としてこの世に生まれ、長い間保育器の中で過ごしていました。そんな息子も今では小学校5年生になり、元気に遊んでいる姿を見るたびに、命の尊さを感じます。
現職についてですが、平成21年に消防士として採用され、平成22年に救急課程を修了し、救急隊員としての資格を得ました。そして、平成31年に救急救命士国家試験を合格し、現在は救急救命士として、救急業務を行っています。専属ではないので、日によっては火事や水災害、地震などの事案に、消防隊として対応します。
このコラムでは「救急救命士」の立場として、お話をしていきたいと思いますので、よしくお願いします。
さて、救急救命士という言葉に聞き覚えがあったとしても、具体的にどのようなことができるのか、認識されている方は多くないのではないでしょうか?お恥ずかしい話、私は消防士になるまで、救急救命士に関する知識は皆無でした。…ですので少しだけ、救急救命士について説明させていただきます。
平成3年に救急救命士法が制定され、翌年に救急救命士が誕生しました。
救急救命士と救急隊員の違いは「救急救命処置」を施せるか否かです。救急救命処置とは、重度傷病者に対して行う処置のことですが、中でも医師の具体的な指示を受けて行うものを「特定行為」といい、輸液(点滴)や薬剤投与(アドレナリン、ブドウ糖)、気管挿管などの処置を行えます。ただし、相応の現場経験や、病院実習を経て、認定を受ける必要があります。
ありがたいことに、私は現在救急救命士が行える特定行為、すべて認定を受けています。今後、特定行為が追加になった際は、さらに病院実習を行い、認定を受けることで、現場活動の幅が広がっていくことになります。
私は救急救命士歴数年の、経験未熟な田舎者ですが、救急救命士になって学んだことがたくさんあります。その中で強く感じるのが、心肺停止傷病者に対して「救急救命士は無力」だということです。
なぜそう感じるのかというと、人間は心臓が停止してから10分間なにも行われない状態でいると、生存率は限りなくゼロに等しくなります。しかし、救急隊が出動して現場に到着するまでの、全国平均時間は約10.3分(令和5年)というデータがあります。つまり、救急隊が到着した時点で、助かる確率はゼロに等しいということです。
この事実に直面し、私は特定行為の技術向上に加え、住民の救命に対する意識改革に力を入れるようになりました。本来救急業務の中に「救急講習会」という、住民の方に対して心肺蘇生法やAEDの使い方など、応急手当てを普及するといったことも含まれていますが、どうすればより広く深く普及することができるのか苦慮しました。
意識改革なんて簡単に言いましたが、他者の意識を変えるということは、並大抵のことではないと理解しています。自分にそんな力はないと、自覚もしていました。そこで私は本を読み漁り、偉人の力に頼ることにしました。D・カーネギーさんの「人を動かす」や岡本純子さんの「世界最高の話し方」、伊藤羊一さんの「1分で話せ」は、特に勉強になりました。
本を読んだだけではなにも変わりませんが、自分のアクションに少しずつ取り入れることで成功を積み上げ、自信に繋げることができます。
その甲斐あって、今では受講者の方から「とても分かりやすかった」「またお願いね」など、温かい言葉をいただくようになりました。
私はよく、救急講習会で「皆さんの目の前にいる人が突然倒れたら、どのような行動を取りますか?」と問うようにしています。すると一瞬で空気が張り詰め、受講者が緊張するのを感じます。「他人事」から「自分事」に変える一つの工夫ですが、なかなか効果があると実感しています。
救急救命士として、観察や処置の知識や技術向上はもちろん大切です。しかし、それ以上に、住民と協力して「大切な命」を、最高の形で病院まで搬送することが、傷病者の方に対する最高の医療提供だと思います。
救急救命士「だけ」では無力…。自分の無力さを認め、協力して目的を達成する糸口を見つけることが、人間として生きていく上で大切なことだと学びました。
読みづらい文章をここまで読んでいただき、ありがとうございます。このコラムを読んでくださっている方は、心理学を学ばれている方が多いと思います。そこで、心因性に関する内容として「精神疾患がある方への対応」について、お話ししたいと思います。
私が実際に対応した救急事案では、パニック障害による過呼吸やうつ病によるオーバードーズ(過量服薬)、認知症の高齢者が家に帰れず低体温になったなど、多岐にわたります。躁状態の傷病者が、救急車の運転席に乗り込んでくるといった危ない場面もありました。
いずれにせよ、傷病者への対応だけでなく、家族からの情報収集や、搬送先の医療機関との連携、場合によっては警察の出動要請も考慮しなくてはいけません。
精神疾患は解明されていない部分が多く、処方されている薬や服薬状況によっても症状は様々なので、救急隊としてはとても神経を使います。
…と、ぐちぐちいっても仕方がないので、皆さんにとって知りたいのは「どんな症状が出たら、救急車を呼ぶべきなのか?」というところだと思います。
基本的に救急隊は、要請があれば現場に向かい、傷病者を適切な病院へ搬送します。しかし、もし余裕があれば、傷病者の「かかりつけ医」や「精神科救急情報センター」へ問い合わせて、指示を仰いでみてください。その結果「救急車で来てください」と言われたら119番通報ですし、「自家用車で来てください」と言われたら、自家用車やタクシーで病院に向かえばいいわけです。
精神疾患以外でも、救急車を呼ぶべきか悩む場合は、#7119(救急安心センター事業)や救急受診アプリ「Q助」を利用してみてください。こういった行動が、救急車の適時・適正利用に繋がり、救命率向上の後押しになります。
また、精神疾患を有する方は「状況を理解できていない」ことに、恐怖と苛立ちを感じます。
日常会話の中で「今日は⚪︎月⚪︎日だね」「朝食べた⚪︎⚪︎美味しかったね」など、状況を把握できる内容を会話の中にさりげなく組み込むのもいいみたいですよ。
私は心理学に関する知識は皆無で、むしろ人の気持ちを察知する能力が、欠落しているとさえ思います。そのため、妻とはよく喧嘩をするし、子供たちの機嫌を損なってしまう日々です(笑)これを機に、私も心理学について学んでいきたいと考えています。
現代では高齢者の認知症やうつ病、若年者の不安障害やパニック障害、ADHDなど様々な悩みを抱える人々に溢れています。共に協力して、より住みやすい世の中を作っていきましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
【つぶ@田舎の救命士】
平成21年に消防士として採用され、平成22年に救急課程を修了し、救急隊員としての資格を得ました。そして、平成31年に救急救命士国家試験を合格し、現在は救急救命士として、救急業務を行っています。専属ではないので、日によっては火事や水災害、地震などの事案に、消防隊として対応。
2児の父親でもある。